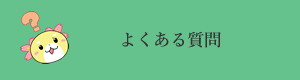後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度とは
この制度は、誰もが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平でわかりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的としてつくられた独立した医療保険制度です。
75歳以上の方(申請により一定の障害があると認定を受けた65歳以上の方を含む)は、国民健康保険や被用者保険などの公的医療保険から、後期高齢者医療制度へ移っていただくことになります。
制度の運営は、埼玉県内のすべての市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料率の決定並びに被保険者ごとの保険料賦課額の決定、医療を受けたときの給付や財政運営を行います。一方、市町村では、資格確認書の引き渡し、保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの被保険者の皆さんにとって身近な窓口業務を行います。
被保険者は一人ひとりが保険料を納め、マイナ保険証や埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付する資格確認書等を医療機関に提示して診療を受けます。
被保険者となる方
- 75歳以上の方(生活保護受給者等を除く)
- 65歳から74歳の方で一定の障害があると埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
認定を受けるには申請が必要です(「障害認定申請」といいます)。
※障害認定については、障害認定とはをご覧ください。
被保険者になる日
- 埼玉県内在住で75歳になる方
75歳の誕生日から - 75歳以上の方が、他の都道府県から埼玉県に転入したとき
転入した日から - 65歳から74歳で一定の障害のある方
障害認定申請をして認定を受けた日から
後期高齢者医療資格確認書
令和6年12月2日以降に75歳になる方には「後期高齢者医療資格確認書(資格確認書)」を誕生日の前日までにご自宅に郵送します。有効期限は令和7年7月31日です。すでに資格を取得していて、お手元に有効期限が令和7年7月31日の「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」をお持ちの方は、有効期限まで保険証をご使用いただけます。
有効期限後(令和7年7月31日以降)の被保険者証の取扱いについて
マイナンバーカードをお持ちの方は、利用登録をすることでマイナンバーカードを保険証として使用できます。マイナンバーカードをお持ちでない方、またはマイナンバーカードを持っているが、利用登録を行っていない方には「後期高齢者医療資格確認書(資格確認書)」を交付します。
医療機関等にかかるとき
医療機関等にかかるときは、マイナ保険証、資格確認書または保険証で受診できます。
詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用をご確認ください。
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます(負担していただく割合は、資格確認書または保険証に記載されています。この割合を「一部負担金の割合」といいます)。
一部負担金の割合は次のとおりです。
- 一般 1割または2割
- 現役並み所得者 3割
住民税課税標準所得金額が145万円以上である被保険者と、その同じ世帯に属する他の被保険者は、「現役並み所得者」となり、一部負担金の割合は3割になります。ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、1割または2割負担になります。
- 被保険者が一人の世帯
被保険者の前年中の収入金額が383万円未満。ただし、収入金額が383万円以上であっても、同じ世帯に70歳から74歳の方がいて、その方と被保険者の収入金額の合計が520万円未満。 - 被保険者が二人以上の世帯
被保険者全員の前年中の収入金額の合計が520万円未満 - 世帯の被保険者全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下(平成27年1月1日から適用)
収入金額とは、所得税法第36条第1項に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません)
(収入の例 利子収入、配当収入、給与収入、雑収入、不動産収入、事業収入、山林収入、譲渡収入、一時収入)
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告した場合や、所得金額が0円またはマイナスになる場合でも、その収入の合計額が上記1、2の基準額を超える場合は、要件に該当しなくなります。
旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。多くの場合、収入から必要経費を引いた「所得」から43万円を差し引いた額になります。
関連ホームページ
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
- 埼玉県庁(国保医療課)<外部リンク>
- 厚生労働省(後期高齢者医療制度)<外部リンク>