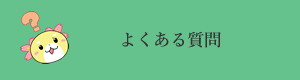令和7年度国民健康保険税
国民健康保険に加入していると、医療機関での御本人様の医療費の支払いが一部のみとなります。残りの医療費は国民健康保険が負担するので、もしものときでも安心して医療が受けられます。この国民健康保険が負担する医療費の財源となっているのが国民健康保険税です。
以下をクリックしていただくと、国民健康保険税の試算ができます。
令和7年度国民健康保険税試算 [Excelファイル/128KB]
過年度および令和8年度(令和7年12月末現在)の試算については、以下のページを御活用ください。
令和7年度の国民健康保険税は次の医療保険課税分、後期高齢者支援金課税分、介護納付金課税分の合計額となります。
国民健康保険制度は、市からの繰入金、国や県などからの補助金と、加入者が負担する国民健康保険税を財源に運営していますが、一人あたりの医療費の増加などにより、補助金や国民健康保険税だけでは財源を確保できない状況が続いています。これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響や、社会情勢などを鑑み、その不足分を基金や法定外繰入金を活用し補ってきましたが、基金も減少し、大変厳しい財政状況となっています。
また、平成30年度からは県が国民健康保険制度の運営主体となったため、市町村は県に納める国民健康保険事業費納付金の財源となる国民健康保険税の税率などを県が示す標準保険税率を参考に決定することになりました。埼玉県では原則として、同一所得かつ世帯構成が同じであれば、どこの市町村に住んでいても国民健康保険税は同じ金額に統一することを目指していますが、標準保険税率と現在の本市の保険税率とは大きな差がある状況となっています。
このようなことから、健全に国民健康保険を運営するため、税率の改正が必要となりました。令和7年度の国民健康保険税については下記のとおりです。今後も保険税の見直しを検討していきます。今回の見直しは、国民健康保険に加入する皆さんの負担が増加することになりますが、今後とも国民健康保険の運営にご理解ご協力をよろしくお願いします。
令和7年度 国民健康保険税の算出方法
| 課税の基礎 | 医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40歳以上64歳までの方) |
|
|---|---|---|---|---|
|
所得割額 |
(令和6年中の所得金額-43万)×右の税率 | 7.84% | 2.33% | 1.98% |
|
均等割額 |
被保険者1人ついて | 32,200円 | 10,100円 | 13,700円 |
| 課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | |
- 世帯内の国民健康保険加入者(0~74歳)について、加入者ごとに医療保険分、後期高齢者支援金分の所得割額と均等割額を計算します。
- 世帯内に40歳から64歳までの方がいる場合は、その人の介護納付金分として所得割額と均等割額を計算します。
- 基礎控除額(43万円)は、合計所得金額が2,400万円以上の場合、段階的に減少します。
- 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。(国民健康保険に加入していない世帯主でも、擬制世帯主として納税義務者となります。)
国民健康保険税の軽減
世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割額が軽減されます。(申請不要)
| 軽減区分 | 軽減判定所得 |
|---|---|
| 7割軽減基準額 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割軽減基準額 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+30.5万円×(被保険者数) |
| 2割軽減基準額 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+56万円×(被保険者数) |
※給与所得者等の数とは、世帯主、加入者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者(55万円を超える給与収入を有する方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える公的年金等の支給を受ける方で給与所得を有しない方)のそれぞれの合計数です。
令和4年度から未就学児の国民健康保険税が軽減されます。(申請不要)
令和4年度から未就学児における国民健康保険税の均等割額が2分の1に軽減されます。所得に応じた軽減が適用されない世帯の世帯員でも、こちらの軽減は適用されます。
| 所得に応じた軽減区分 | 未就学児における軽減割合 |
|---|---|
|
7割軽減 |
7割+1.5割(残り3割の1/2)=8.5割軽減 |
|
5割軽減 |
5割+2.5割(残り5割の1/2)=7.5割軽減 |
|
2割軽減 |
2割+4割(残り8割の1/2)=6割軽減 |
|
軽減なし |
5割軽減 |
納税通知書の発送と納期限について
令和7年度国民健康保険税納期限
普通徴収(納付書や口座振替により納める)の世帯は7月以降の9回に分けて国民健康保険税を納めていただきます。なお、特別徴収(年金からの引き落とし)の対象の世帯は、年金給付日に年金から保険税を差し引いて納めていただきます。各納期限は下記のとおりです。
普通徴収の納期限
7月31日(第1期)、9月1日(第2期)、9月30日(第3期)、10月31日(第4期)、12月1日(第5期)、12月25日(第6期)、2月2日(第7期)、3月2日(第8期)、3月31日(第9期)
※7月の中旬に納税通知書を発送いたします。
特別徴収の納期限
各年金給付日
|
特別徴収の区分 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限 |
4月の年金 から引落し |
6月の年金 から引落し |
8月の年金 から引落し |
10月の年金 から引落し |
12月の年金 から引落し |
2月の年金 から引落し |
※新たに仮徴収が始まる世帯には、3月頃に通知を送付いたします 仮徴収税額は、前年度の国民健康保険税より算定します。(前年度も特別徴収だった世帯は、2月の本徴収税額と同額となります。)10月以降の本徴収税額は、前年の所得確定後の7月に通知いたします。
国民健康保険税計算例
普通徴収の世帯(例)
- 太郎(56歳)会社退職:令和6年中の給与収入400万円(所得276万円)
- 花子(54歳)パート:令和6年中の給与収入120万円(所得65万円)
- 一郎(17歳)高校生:収入なし
医療保険課税分
- A:所得割税額
太郎(276万円-43万円)×7.84%=182,672円
花子(65万円-43万円)×7.84%=17,248円 - B:均等割税額
3人×32,200円=96,600円
医療保険課税分合計 296,500円(100円未満切捨)
後期高齢者支援金課税分
- A:所得割税額
太郎(276万円-43万円)×2.33%=54,289円
花子(65万円-43万円)×2.33%=5,126円 - B:均等割税額
3人×10,100円=30,300円
後期高齢者支援金課税分合計 89,700円(100円未満切捨)
介護納付金課税分(40歳以上65歳未満の方のみ対象)
- A:所得割税額
太郎(276万円-43万円)×1.98%=46,134円
花子(65万円-43万円)×1.98%=4,356円 - B:均等割税額
2人×13,700円=27,400円
介護納付金課税分合計 77,800円(100円未満切捨)
医療保険課税分+後期高齢者支援金課税分+介護納付金課税分=464,000円(12ヶ月分)
上記の計算により坂戸太郎さんの家族3人の国民健康保険税額は464,000円となり、年間9回に分けて納めていただくこととなります。
納期
- 第1期:52,000円(納期限:7月31日)
- 第2期:51,500円(納期限:9月1日)
- 第3期:51,500円(納期限:9月30日)
- 第4期:51,500円(納期限:10月31日)
- 第5期:51,500円(納期限:12月1日)
- 第6期:51,500円(納期限:12月25日)
- 第7期:51,500円(納期限:2月2日)
- 第8期:51,500円(納期限:3月2日)
- 第9期:51,500円(納期限:3月31日)
特別徴収の世帯(例)※前年度の保険税を特別徴収により納めていた世帯
一郎(72歳)年金:令和6年中の年金収入240万円(所得130万円)
※前年度の2月の特別徴収税額18,500円
医療保険課税分
- A:所得割税額
一郎(130万円-43万円)×7.84%=68,208円 - B:均等割税額
1人×32,200円=32,200円
医療保険課税分合計 100,400円(100円未満切捨)
後期高齢者支援金課税分
- A:所得割税額
一郎(130万円-43万円)×2.33%=20,271円 - B:均等割税額
1人×10,100円=10,100円
後期高齢者支援金課税分合計 30,300円(100円未満切捨)
医療保険課税分+後期高齢者支援金課税分=130,700円(12ヶ月分)
4月、6月、8月の特別徴収(仮徴収)税額
前年度の2月の特別徴収税額(18,500円)
10月、12月、2月の特別徴収税額
130,700円-(18,500円+18,500円+18,500円)=75,200円
75,200円÷3(10月以降の年金給付回数)=25,066円
納期
- 第1期:18,500円(令和7年4月の年金給付より引き落とし)
- 第2期:18,500円(令和7年6月の年金給付より引き落とし)
- 第3期:18,500円(令和7年8月の年金給付より引き落とし)
- 第4期:25,200円(令和7年10月の年金給付より引き落とし)
- 第5期:25,000円(令和7年12月の年金給付より引き落とし)
- 第6期:25,000円(令和8年2月の年金給付より引き落とし)
特別徴収の世帯(例)※この年度の4月より特別徴収が始まる世帯
- 次郎(72歳)年金:令和6年中の年金収入240万円(所得130万円)
- 貴子(70歳)年金:令和6年中の年金収入195万円(所得85万円)
※前年度の国民健康保険税額(年税額)180,000円
医療保険課税分
- A:所得割税額
次郎(130万円-43万円)×7.84%=68,208円
貴子(85万円-43万円)×7.84%=32,928円 - B:均等割税額
2人×32,200円=64,400円
医療保険課税分合計 165,500円(100円未満切捨)
後期高齢者支援金課税分
- A:所得割税額
次郎(130万円-43万円)×2.33%=20,271円
貴子(85万円-43万円)×2.33%=9,786円 - B:均等割税額
2人×10,100円=20,200円
後期高齢者支援金課税分合計 50,200円(100円未満切捨)
医療保険課税分+後期高齢者支援金課税分=215,700円(12ヶ月分)
4月、6月、8月の特別徴収(仮徴収)税額
180,000円(前年度の国民健康保険税年税額)÷6(この年度の年金給付回数)=30,000円
10月、12月、2月の特別徴収税額
215,700円-(30,000円+30,000円+30,000円)=125,700円
125,700÷3(10月以降の年金給付回数)=41,900円
納期
- 第1期:30,000円(令和6年4月の年金給付より引き落とし)
- 第2期:30,000円(令和6年6月の年金給付より引き落とし)
- 第3期:30,000円(令和6年8月の年金給付より引き落とし)
- 第4期:41,900円(令和6年10月の年金給付より引き落とし)
- 第5期:41,900円(令和6年12月の年金給付より引き落とし)
- 第6期:41,900円(令和7年2月の年金給付より引き落とし)
国民健康保険税は個人の収入状況・世帯状況によって算定いたします。上記の例とは異なることがありますので御注意ください。
詳しくは、健康保険課国民健康保険係へ