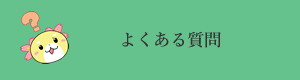医療費が高額になったとき(高額療養費)
自己負担限度額について
同じ診療月に支払った医療費の自己負担額の合計額が自己負担限度額(以下「限度額」という。)を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。初めて高額療養費の支給に該当した方には、お知らせと申請書をお送りします。
| 所得の区分 | 負担割合 | 外来のみ(個人ごと) |
入院+外来(世帯合算) |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) |
|
| 現役並み所得者2 | 3割 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) |
|
| 現役並み所得者1 | 3割 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円) |
|
| 一般2 | 2割 |
18,000円または 【6000円+(医療費-30,000円)×10%】 の低い方を適用 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数該当44,400円) |
| 一般1 | 1割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
|
| 低所得者2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 1割 | 15,000円 | |
- 現役並み所得者3とは、課税所得690万円以上の方。
- 現役並み所得者2とは、課税所得380万円以上690万円未満の方。
- 現役並み所得者1とは、課税所得145万円以上380万円未満の方。
- 一般2とは、自己負担2割の方。
- 一般1とは、現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しない方。
- 低所得者2とは、世帯員全員が住民税非課税である方。
- 低所得者1とは、世帯員全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある方は、10万円を控除して計算)である世帯の方。
75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額の特例
75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。(1日生まれの方を除く。また、障害認定により75歳の誕生日前に後期高齢者医療制度に加入した方は対象となりません。)
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
令和6年12月2日以降、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は発行されなくなりました。
各証をお持ちでなく、今後必要となる方は、「令和6年12月2日以降の高額療養費における限度額適用について」を参照して下さい。
| 区分 | 証の種類 |
|---|---|
| 現役並み所得者1・2 | 限度額適用認定証 |
| 低所得者1・2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
有効期限が令和7年7月31日の各証をお持ちの方は有効期限まで各証をお使いいただけます。医療機関の窓口に提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額まで抑えることができます。また、入院したときに医療機関の窓口で各証を提示することで、自己負担額のほか、入院中の食事・生活療養標準負担額も減額されます。
| 所得区分 | 食事療養 標準負担額 (1食あたり) |
生活療養標準負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | ||||
| 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
| 現役並み所得者 | 510円 | 510円(注2) | 370円 | 510円(注2) | 370円 |
| 一般1、2 | |||||
| 低所得者2 (区分2) |
240円 (注1) |
240円 | 370円 | 240円 (注1) |
370円 |
| 低所得者1 (区分1) |
110円 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | |
- 注1 過去12か月に90日を超える入院があったとき(長期入院)は、1食あたり190円。
- 注2 管理栄養士または栄養士により、栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関以外の場合は、1食あたり450円。
令和6年12月2日以降の高額療養費における限度額適用について
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されなくなりました。なお、有効期限が令和7年7月31日の各証をお持ちの方は有効期限まで各証をお使いいただけます。
令和6年12月2日以降、各証をお持ちでない方も次のとおり高額療養費における限度額適用を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証で受診してください。限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、非課税世帯の方は、入院中の食事・生活療養標準負担額も減額されます。
マイナ保険証をお持ちでない方
限度額区分が記載された資格確認書で受診してください。高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また非課税世帯の方は、入院中の食事・生活療養標準負担額も減額されます。
資格確認書に限度額区分が記載されていない方は、申請が必要です。申請に基づき、限度額区分を記載した資格確認書を交付します。資格確認書をお持ちいただき、窓口で申請してください。
令和7年7月31日期限の保険証をお持ちの方も、申請が必要です。申請に基づき、限度額区分を記載した資格確認書を交付します。保険証をお持ちいただき、窓口で申請してください。
※現役並み所得者3、一般1、2に該当している方は申請は不要です。保険証または資格確認書を病院等に提示することで、一定の限度額が適用されます。限度区分について詳しくは下記担当までお問合せください。